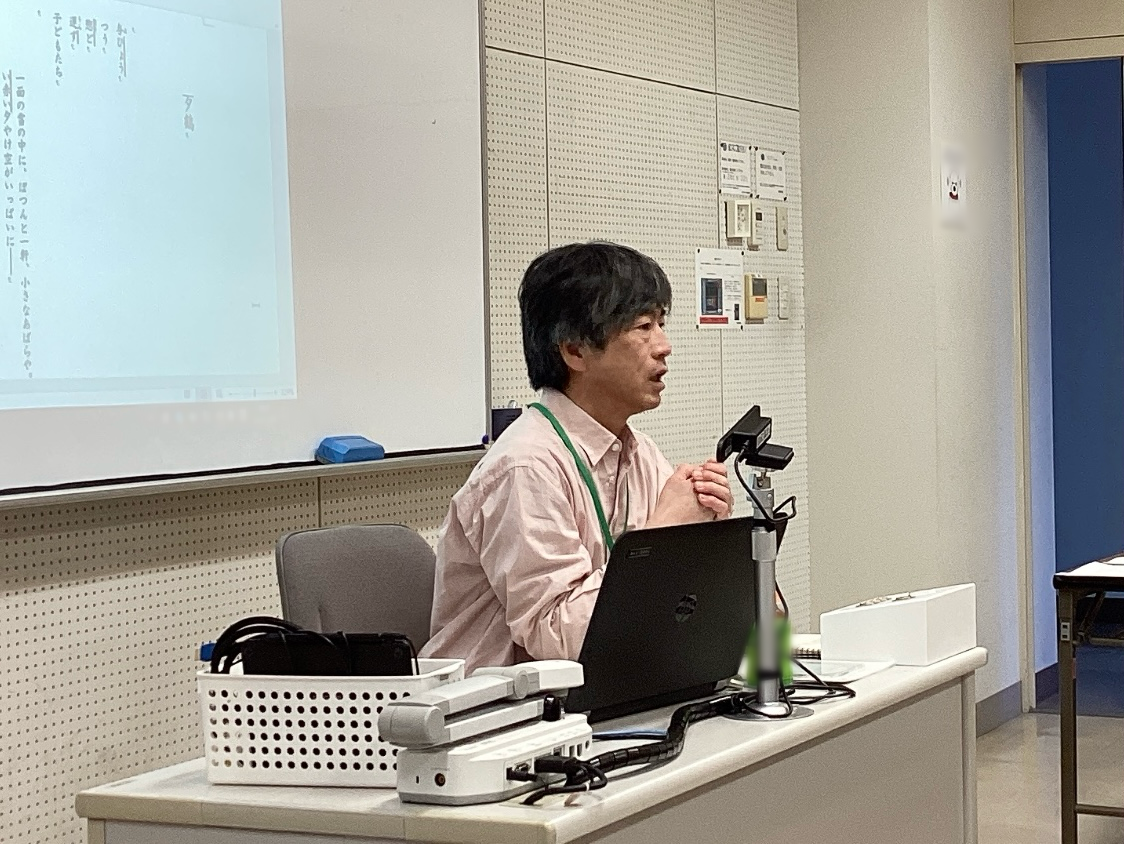安冨順先生ご担当の「国語国文学特講(演劇)Ⅱ」の授業において、演出家の冨士川正美先生(桐朋学園芸術短期大学芸術科演劇専攻・常勤講師)をゲストスピーカーにお招きしました。
登場人物の台詞や、ト書と呼ばれる、所作などを示したごく短い文を中心に構成された、いわゆる演劇台本のような文学作品のことを戯曲と言います。(ト書は、もとは歌舞伎の台本から来た言葉です。)
講演会では木下順二の『夕鶴』が取り上げられました。昔話の鶴の恩返しをもとに書かれた作品だと言われています。初出と初演情報、上演スタイルや上演当時の時代背景を確認した後、学生たちは、冨士川先生から役を振られ、実際に声に出して読み進めていきました。
戯曲を読む時にはまず、場面で段落分けをするそうです。第何番の場面なのか、便宜上の場面割りをすることは、お稽古への段取りという側面もあって重要であり、場面割りをしながら演出家は台詞やト書から、今、何が起きているのか、どんな状況なのか、誰が何をしたのかをはっきりさせます。その際、何が目的で、もしくは何がきっかけでそうするのか、といった直接は書かれていない部分の意味を読み取ることが〈戯曲を読む〉上では最も大事なのだとわかりました。例えば作品冒頭、「与ひょう」がいろりの傍で眠りこけていることが書かれていますが、これは決して「与ひょう」が怠け者であるからではなく、「つう」の帰りを待っていたからだと読み取ることで、「与ひょう」は「つう」なしに生きてはいけないのではないかという作品結末の伏線、暗示であったことが読み解けていくのです。(近世戯曲だとこのような伏線をしこみと言い、しこみが明らかになって終わりに向かうことをほどきと言うそうです。)
ロマンティックに作品を読み込んでいき、最後には争いや平和、理想と現実について、強いメッセージを学生たちは受け取っていました。