修士課程の成果を基盤に、言語・文学研究の新しい地平を見出す
専攻主任メッセージ
言葉は文化、歴史、思想を映し出す鏡であり、単なるコミュニケーションの道具にとどまりません。本専攻では、日本語、フランス語、英語という異なる言語を軸に、多角的な視点から文学、言語学、教育、文化論などを深く掘り下げ、新たな知の創造を目指します。オムニバス授業では、各分野の専門家が集い活発な議論を展開、異なる視点に触れ、自身の研究を深めることができます。特定の研究領域を深めながら、同時に幅広い教養を身につけ、多様な問題解決能力を養います。既成概念にとらわれず、常に新しい知識を求める探究心、異なる分野の知識を結びつけ、複雑な問題を分析する能力、自分の考えを明確に表現し、論理的に展開する能力といったスキルが求められます。言葉の奥深くに隠された秘密を解き明かし、新たな知の扉を開きましょう。
本専攻の特色
- 特定の研究領域を選び、主体的かつ専門的に研究する「専門科目」と、学際的な研究を推し進めるための「関連科目」を設置しています。
- オムニバス授業では、異なる分野の専門家と議論を深め、新たな視点から世界を見つめることができます。
専攻主任 岩政 伸治

大学院生の声
修士課程修了後に社会人を経験し、博士課程に戻りました。大学院での学びで得たのは、ひとつのものごとを徹底的に調べ、広げるだけ広げて最終的にテーマに戻ってくる作業ができたこと、ものごとを柔軟に多角的に捉える視点が身についたこと、より深く考えるようになったことです。
現在は私立の中高一貫校で学校司書をしておりますが、利用者の知りたい情報について、何を知りたいか、その情報をどう使うか、用途によって資料の出し方が変わるので、大学院で調べ方も含め、調べて考えることをくり返し練習できたことはよかったです。そして、働いてから学ぶと、様々なことがらについて実務に結びつけて理解することができました。
(2016年度単位取得満期退学)
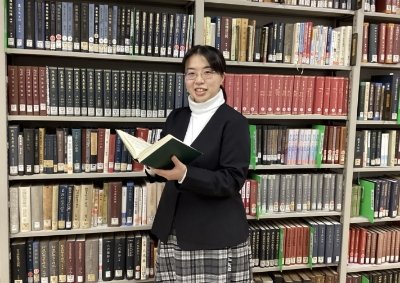
指導教員紹介
日本語学・日本文学分野
| 教員名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 猪狩 友一 教授 | 近代文学、ことに明治期の文学について 国木田独歩や樋口一葉などの明治期の文学の研究、巖谷小波の日記の翻刻・研究。「美術」「恋歌」「一人称」などのテーマに興味があります。 |
| 伊東 玉美 教授 | 中世の価値観を探る 主に平安時代末から室町時代にかけての文学作品を中心に、歴史史料、絵巻物など、様々なジャンルの資料を参照しながら、時代の知識や発想の再現を目指しています。 |
| 井上 隆史 教授 | 近代文学、思想、カルチャー 三島由紀夫、大江健三郎を中心に、文学、哲学、社会現象についてジャンルを超えて幅広く研究しています。 |
| 川瀬 卓 教授 | 日本語の副詞の歴史的研究 副詞を視点とした日本語文法史へのアプローチを試みています。個々の副詞の歴史変化を明らかにするだけでなく、それを通して、文法変化のあり方、日本語の歴史の時代的動向についても把握することを目指しています。 |
| 小林 明子 教授 | 近現代文学の作品について、その構造を探究する 明治・大正期の作品を中心に、個々の作品世界が構築された過程を、作家の創作意識や作品の周辺にある要素(国内外の政治、社会、思想など)の動向を視野に入れ、資料を参考にしながら多面的に検討します。 |
| 武田 加奈子 教授 | 接触場面の研究 外国につながる子どもが置かれている状況から日本語使用時の言語問題まで幅広く考えられるよう、接触場面ではどのような現象が起こっているのか、さまざまな観点から捉え、参加者の視点から分析していきます。 |
| 常盤 智子 教授 | 外国人の日本語研究から日本語について考える 幕末から明治にかけて、多くの外国人が来日して、日本語の勉強をしています。それらの記録や教科書を読み解くことで、当時の日本語を探っていきたいと考えています。 |
| 名木橋 忠大 准教授 | 近現代詩の原理を探る 詩という言語表現が明治から昭和にかけてどのように形成されていったのかを研究しています。文芸思潮、思想、宗教、他芸術の動向など、詩人を取り巻いた環境は詩語の形成にどう作用したでしょうか。 |
| 萩野 了子 講師 | 古代和歌の修辞技巧の研究 奈良時代から平安時代に詠まれた和歌の修辞技巧が、どのような表現構造を持っているか、なぜ用いられるのか、当時の人々がそれらをどれほど意識しているのか、といったことに関心があり、勉強しています。 |
フランス語学・フランス文学分野
| 教員名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 海老根 龍介 教授 | ボードレールを中心とした19世紀フランス文学 ボードレールを出発点に、19世紀以降のフランス近現代詩全般の理解を目指しています。19世紀における芸術的実践と社会との関係の解明も研究課題としています。 |
| 越 森彦 教授 | ジャン=ジャック・ルソーのレトリック、レトリックの知見を活用した文学研究(修辞学的読解)の方法論 稀代の論争家ルソーの論法や文彩を解明し、修辞学の視点を活かした文学作品の多角的な読み解きを研究します。 |
| 辻川 慶子 教授 | 19世紀フランス文学、歴史と文学、リライト、大衆文化とメディア 19世紀フランス文学、主にネルヴァルとロマン主義を専門としています。これまで歴史と文学、文学作品とリライトの問題を研究してきました。現在はロマン主義時代の大衆文化とメディアに関心を持っています。 |
| 善本 孝 教授 | 20世紀フランス小説、フランス語教育、コミュニケーション論 文学ではアルベール・カミュを専門としています。フランス語教育では外国語教育/学習をコミュニケーション論の視点から研究しています。 |
| 大塚 陽子 准教授 | フランス語、フランス語会話分析 日本におけるフランス語教育のあり方や可能性について探究しています。また、フランス語の「会話」にも関心があり、対人関係を調整し得る言語の機能「ポライトネス」に関わるフランス語の諸現象も研究対象です。 |
| 畠山 香奈 准教授 | 17世紀フランス文学、古典主義悲劇研究 専門は17世紀フランス文学、悲劇、演劇史。ジャン・ラシーヌに代表される古典主義悲劇の成立をアリストテレス『詩学』の受容をとおして演劇史的に研究しています。 |
| ブルネ トリスタン アンリ 准教授 | サブカルチャーの歴史 フランスと日本のサブカルチャー(漫画/BDとアニメを中心にして)とその関係の歴史を研究しています。その裏にある思想史と精神史にも関連するようにサブカルチャーの歴史を研究もします。 |
| 村中 由美子 准教授 | ユルスナールを中心とした20世紀フランス文学 ユルスナールを出発点に、20世紀の文学・芸術思潮を参照しつつ、絵画と文学の関わり、文学作品の映画化といった切り口から作品の研究をしています。ジェンダーの問題にも関心があります。 |
| デムチナ アリア 講師 | アニメーション映画の美学史と技術史 フランスのアニメーション映画の美学、技術、産業の在り方を歴史の視点から研究しています。その周辺として、美術史、実写映画史、20-21世紀の視覚文化に触れることもあります。 |
英語圏・国際社会文化分野
| 教員名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 岩政 伸治 教授 (専攻主任) |
アメリカの文学・文化(エコクリティシズム、比較文化、環境思想) 比較文学、特にネイチャー・ライティングと呼ばれるジャンルを中心に、環境批評、環境思想とメディアリテラシーの問題を取り上げます。あわせて翻訳理論についても扱う予定です。 |
| 土井 良子 教授 | イギリス近代文学(18-19世紀小説中心)・文化 習作から出版作まで、作品を通して浮かび上がる作家(特に女性作家)の自己形成に関わる諸問題や、作品の同時代から現代までのafterlife(受容史・アダプテーション作品など)に注目しています。 |
| ナイト ティモシィ 教授 | Language in Society The course is conducted in English. With guidance, students can explore their interests in language as shown in journalistic media, advertising, a chosen linguistic landscape, or researching language use through corpus linguistics, or a combination of these. |
| 平尾 桂子 教授 | 家族社会学、ジェンダー社会学 家族・教育・労働をジェンダーの切り口で考えること。たとえば、家族内での男女の役割や権力関係、男女の賃金格差との関係など。 |
| 水越 あゆみ 教授 | イギリス文学、英語詩 ロマン主義時代の文学研究を切り口として、文学作品の審美的価値は歴史的に相対化できるか、「英文学」という制度はどのように構築されたか等の研究課題に取り組んでいます。 |
| 島﨑 里子 准教授 | 英語学(英語史)、古・中英語文学・文化 英語(音韻・統語・意味等)の通時的・共時的変化、古・中英語の文献を読み解き、当時の社会や文化について考えます。 |
| ジョンソン エイドリエン レネー 准教授 | Gender, Feminism, & Cultural Studies In my class students will focus first on learning about different feminist research research methods through readings on methodology, and then look at these methods in action in recent and landmark studies conducted on Japanese society. Of course, all classes, readings, and assignments are completely in English! |
| 箕輪 理美 准教授 | アメリカ史、ジェンダー・セクシュアリティ史 専門は19世紀アメリカ史で、結婚やジェンダー・セクシュアリティに関する問題を主な研究テーマとしています。また、近年はクィア史の分野にも関心を深めています。 |
| 米田 ローレンス正和 准教授 | 近代イギリス思想 啓蒙思想時代からロマン主義時代にかけての歴史叙述を通じて、ギリシア・ローマの古典文学が異教的な文化遺産として継承されていった、そのプロセスの解明に取り組んでいます。 |
専攻教員紹介一覧はこちら
博士論文題目
※博士論文の内容は「白百合女子大学学術機関リポジトリ」で閲覧することが可能です。
| 年度 | 題目 | 副題 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 遠藤周作論 | ─他者評価から解放された〈私〉を求めて |
| 2 | 2018 | 『源氏物語』における『遊仙窟』の受容 | ―「宇治十帖」を中心に |
| 3 | 2016 | T.S.エリオットの初期詩篇を読む | ─「音楽」と「絵画」を中心として─ |
| 4 | 2016 | トマス・ハーディの小説世界 | ─登場人物たちに描き込まれた国際事情と「グレート・ブリテン島」的世界─ |
| 5 | 2015 | 日中両言語における可能表現に関する対照研究 | ―日本語教育における可能表現のあり方について |
| 6 | 2015 | 日本語教育の視点から見る日本語の「の」と中国語の「的」 | ―中国語母語日本語学習者の「の」の誤用を中心に |
卒業後の進路
修了後の進路・キャリアについて
一般企業への就職のほか、大学院で学んだ専門性を生かし、教員や翻訳家、研究者となった修了生もいます。
学部生同様、学生一人ひとりと向き合う丁寧なキャリア支援を行っています。学部生向けに実施しているキャリアサポートのプログラムは、大学院生も参加可能です。












